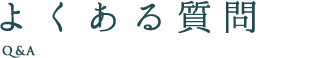
2025年の建築基準法の改正により、増築に限らず、大規模の修繕や模様替え(以下、増築等)でも確認申請が必要となる場合が多くなりました。既存建築物に対する確認申請は、新築時の検査済証の有無によって進め方が大きく変わります。検査済証が発行されていれば、比較的簡単に確認申請の手続きに進むことができます。一方、検査済証がない場合はハードルが高くなりますが、建築基準法の改正に伴い国土交通省の通知やガイドラインが明確になったので、以前よりも進めやすくなりました。
増築等の確認申請は、既存建築物が建築関係法に適法であることを前提としていて、検査済証はそのことを証明する書類です。建築物を新築する場合は、確認済証(申請建物が建築関係法に適法であることを証明する書類)を得て着工し、竣工後に完了検査を受けて検査済証(申請通りに建物が建ったことを証明する書類)の交付を受けます。住宅等の小規模な建築では確認済証は取得しても、検査済証の交付を受けていない(完了検査を受験していない)ケースが昔はよくありました。現在のように検査済証の取得が徹底されるようになったのは、耐震偽装問題が公表された2005年以降です。
検査済証が無いということは、新築時に確認申請通りに竣工したかどうか不明ということになります。そのような状態であっても、建築基準法令の規定への適合状況調査(以下、現況調査)を実施し、適法であることを示すことができれば、検査済証のない建物でも増築等へと進むことができます。2025年より、現況調査によって不適合(違法)部分が判明したとしても、計画建築物全体を建築基準関係規定に適合させる増築等については、柔軟に対応できるようになりました!
◎増築等の確認申請までの流れを整理すると以下のようになります
※木造2階建程度、500平米以下の小規模建築物を想定しています
(0)検査済証が無い?!
↓ ↓ ↓
(1)現況調査(→建築士に依頼:TownFactoryで調査できます)
現行の建築関係法の規定への適合状況を調査します
※既存建築物の図面が無い場合は、実測して復元します
※歴史的建造物の現況調査にも対応できます
↓ ↓ ↓
(2)現況調査報告書の作成
不適合部分がある場合は、増築等工事で一緒に是正できるか検討
↓ ↓ ↓
(3)増築等の設計
既存不適格である規定については緩和を適用して設計
不適合部分がある場合は、増築等工事で一緒に是正できるよう設計
↓ ↓ ↓
(4)増築等の確認申請+工事監理
検査済証がなくても増築等できる方法を探ります、まずはご相談ください
TownFactoryでは現況調査・設計・監理までワンストップで対応できます
2025年11月に国土交通省の既存建築物の現況調査ガイドライン及び既存建築物の緩和措置に関する解説集が更新されました!
![[2950]https://www.townfactory.jp/wp/wp-content/uploads/4cc8f5323d4a67145a7f8b366f63173f.jpg](https://www.townfactory.jp/wp/wp-content/uploads/4cc8f5323d4a67145a7f8b366f63173f-500x173.jpg)
![[2951]https://www.townfactory.jp/wp/wp-content/uploads/cd045574af4d0ffd8aa2595201015de4.jpg](https://www.townfactory.jp/wp/wp-content/uploads/cd045574af4d0ffd8aa2595201015de4-500x191.jpg)